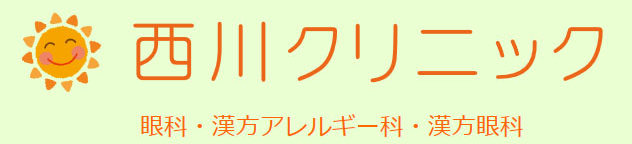毎日寒い日が続きます。冷えるから温めるでは冷え性は解消しない。温陽薬の働きは①諸機能の活性化②生成の基礎③陰の気化④運行の原動力⑤止痛⑥各臓腑の陽に分けて考えます。気化で津液や血を動かしやすくなる。陰液の運行には熱は必要、気の運行には熱の不足を検討し気化不足には温陽が大切です。気血津液の運行の滞りの不足はないか?点検する。温陽薬で理気行気・利湿活血熱は止痛に働く。どの臓腑を温陽するか。肺の表層を温めるのは発散する解表、表層の邪を追い払う散寒薬。しょうにん脈を温める。どこを温める?中心は腎。全体は補陽薬、腎の生殖機能は壮陽薬や助陽薬という。脾は温裏薬、温裏によって温陽で何をもたらすかで利湿薬、活血薬、化痰薬に分けます。何処を温めるかにより温腎薬、温裏薬に分ける。散寒薬(辛温解表)温経止痛薬。附子は側根、烏頭(うず)は主根。大辛燥大熱。腎は12経をつかさどる。附子は燥性収斂、烏頭(漢方エキス製剤にはない)は発散。附子は熱のボリュームを膨らませる。烏頭は表層の腎気を盛り立てつかさどる気を膨らませる。附子は腎陽を増幅します。乾姜は脾、自己免疫疾患にも使う。甘草はショック時のステロイドワンショットのようなところがある。桂枝は細い枝中国では太い幹の部分の皮を肉桂、日本ではニッキ、枝先は桂枝尖で熱のボリューム増やす。桂枝は上昇・発散。腎気を尖通する。心気を縦方向に(深部から浅部)巡らせる。皮膚に陽気を引き出す。。引火起原は桂皮を使って元の場所に戻す。桂枝(桂枝尖)は通絡尖通。附子と桂皮ですがベクトルが烏頭と桂枝は似る。八味丸は寒邪を追い払うための薬だからもとは桂枝今は桂皮。皮と枝を映し間違えたという真柳説がある。腎陽を膨らませるのは桂皮よりも附子である。浮陽(顔が赤くなる)を引火起原するのは附子、深いところの陽気を膨らませるのは附子。呉茱萸は肝脾腎、細辛は腎、乾姜は脾・腎。関西系統中医学講座第3回の腎の生薬を復習してみました。東京の講座から数えてなんか拝聴しただろう、何度聞いても奥深いご講演です。