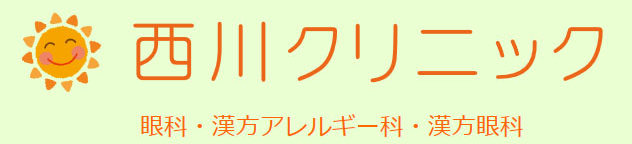わたしたちは現代医学そして日常で筋肉と一つのCONPONENTとしてとらえている。筋と肉に分けて考えることは現代医学では皆無である。筋肉(筋肉)としての形は脾、動きは肝である。脾はそのつまり肉・大きさ・量。筋は動きにかかわる。筋はすじ。腱・筋膜は動きにかかわる。筋(すじ)は肝の指令。指令を伝えるのが肝、骨を動かす。筋肉の収縮は肝、筋量や筋力は脾、指令系統の乱れは筋原性の筋疾患。そして筋肉使わないと廃用性萎縮。筋繊維の数ではなく繊維が細くなると筋原性疾患。(中枢性上位ニューロン)走行。Aは有髄神経BCはむずい神経。筋肉に関係するα、Ia、γ繊維はいずれも有髄繊維。α(白筋)に比べγ(紡錘内筋)は細い神経だそうです。もちろんαβγは太さの順です、太いほうが速い。腎が肝にバトンタッチする肝腎同源。学習を通して肝腎同源で実現する。外からの力に向き合う、伸び縮みを外側に速筋がある持ち上げ支える。速筋は酸素なし無酸素で分解、緩筋は外側、速筋は陽的外側にある。速筋は白筋。緩筋は赤い黒いから赤筋、脾腎と関係が筋肉は一定の緊張度を保ちつつ長さを変化させるので等張力性という。長さが変わらないのが等尺性、筋力・筋量・筋繊維の数は脾が作る。筋芽細胞を腎が作る。繊維の数を増やすのは痛いぐらい疲れると繊維が太くなるのは疲れるから。筋肉増強ですが筋繊維を増やすには使う。構造を支えるには清気を含む肺・心の血液。腎が筋紡錘に与える影響は緩みたるみです。骨よりも固有背筋は緩むから。腎は筋肉の張りを提供する。腎虚はたるむ、腎を鍛えるには歩行ではなく上下移動をする。視点となる腎の補強。腎とかかわる姿勢筋激しい運動や大幅の変異をするものではない。よいのは平地歩行ではなく階段・坂道の上下歩行。筋の病態は脾と腎です。筋原性の委縮では筋委縮は脾や腎です。神経原性の委縮は肝と関係します。。こむら返りには芍薬甘草湯で潤すだけではない。痰飲お血湿濁を考える。たとえば疎経活血湯の出番。全シリーズ40回の関西系統中医学講座の中で仙頭正四郎先生はこの話(筋肉)は一番話したいお話とおっしゃいました。さすが東京科学大医学部からハーバード留学された先生らしい。10月最後の日曜日、この日は朝家を出るときそして姫路駅で大雨傘が必要でした、姫路駅に7時についたのにいきなり赤穂線で動物と衝突し遅延15分がっかり。9月は摂津富田駅構内で不審物(古い便座)が見つかり警察も出動して大迷惑新快速電車は三宮どまりでした。二度あることは三度ある。何もしなくてもしんどい私なのに先月は阪急で中津に行くか普通で大阪まで行くかどんどん仕事が暇になっているので新幹線はもったいない。せっかく寝ていたのになあ。東洋医学辞書が入ってないパソコンで東洋医学の話をするのはかなり手間がいる、高価だが東洋医学辞書を持ち運び用のパソコンにも入れないといけません。と言っても私に残された時間はそんなに長くないあと17か月か。緻密な理論で東洋医学と西洋医学をつなぐ系統中医学講座、WEBになってしまったら寝てしまうだろう。残された時間はそんなに多くない。